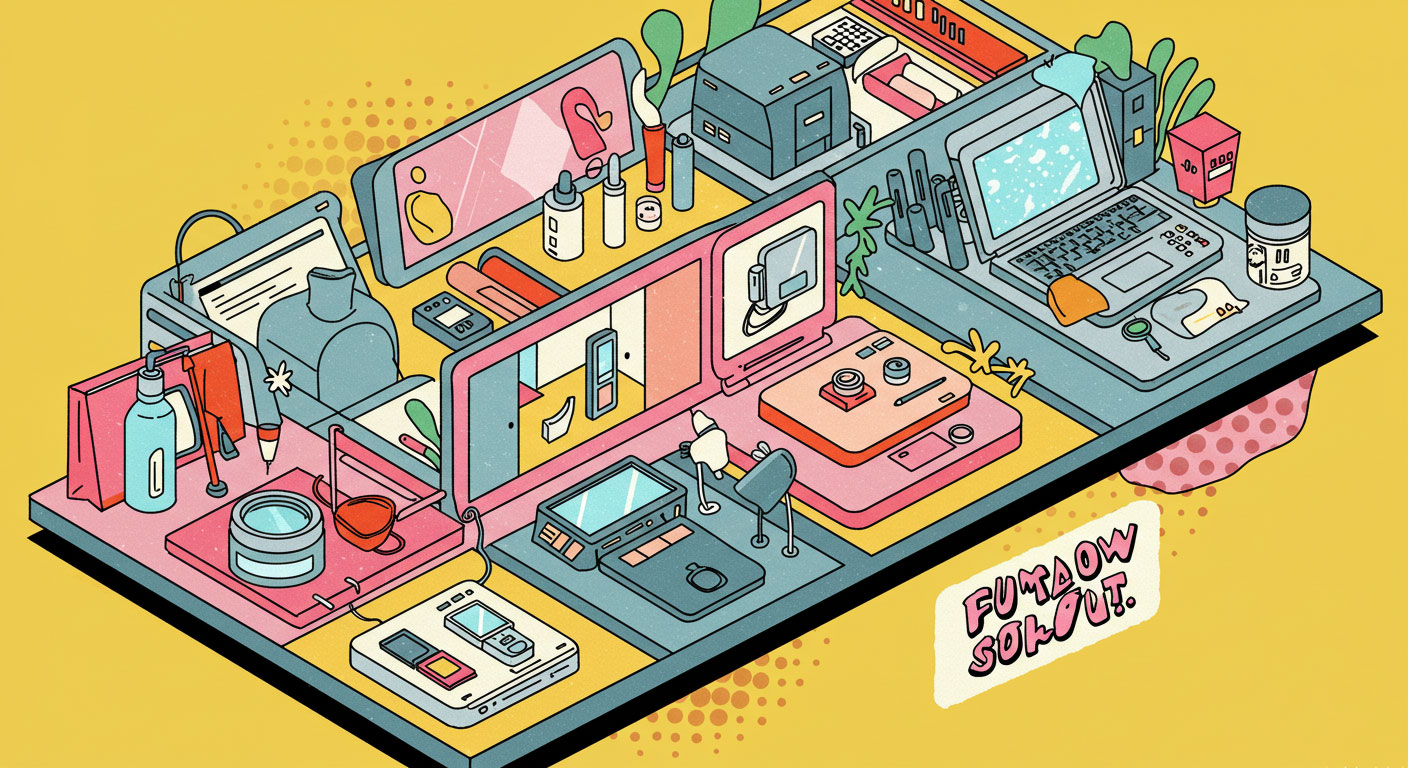ショート動画で“商品を売る”時にやってはいけない構成 売れないのは「商品が悪い」のではなく、「構成がズレている」からかもしれない
はじめに:「バズってるのに、売れない」現象
ショート動画は、今やあらゆる商品のプロモーション手法として欠かせない存在となった。
YouTube Shorts、Instagram Reels、TikTok…。誰もが動画で“物を売る”時代に突入し、企業も個人もその波に乗っている。
けれど、こんな声をよく聞く。
「視聴回数はすごいんです。でも、まったく売れないんです。」
バズったのに売れない。
シェアされたのにクリックされない。
保存されたのに買われない。
それ、本当に“構成”に問題はないですか?
本記事では、ショート動画で「売る」ために、絶対にやってはいけない構成を掘り下げる。
広告代理店が言わない、動画制作会社も教えてくれない、現場でしか見えない「ズレ」の正体を、第三者視点で読み解いていこう。
1. 最初の3秒で「商品」を見せると失敗する理由
ショート動画の鉄則としてよく言われるのが、
「最初の3秒でインパクトを出せ」
このアドバイス自体は間違っていない。
ただ、インパクト=商品そのものと解釈してしまうと、失敗する。
【NG構成例】
0秒〜:「これが話題の◯◯です!」(商品ドン!)
1秒〜:「すごいですよね?」
2秒〜:「ぜひご購入を!」
視聴者の心の声:
「知らんがな」
この“知らんがな構成”は、すでに関心がある人にしか刺さらない。
つまり、購買段階でいうところの「検討後期」だけをターゲットにしてしまっている。
しかし、ショート動画の大半は「たまたま見かけた人」への露出だ。
いきなり商品をぶつけても、関係性も文脈もゼロ。スルーされて当然なのだ。
2. “問題提起”のない動画は、感情が動かない
多くのショート動画は、商品説明からスタートしてしまう。
「何ができるのか」「どう便利なのか」——もちろん大事な情報だ。
でも、人は論理で動かず、感情で動く。
成功している構成に共通するのは「共感型フック」
【OK例】
「朝、時間がない…メイクに15分もかけられない…」
「それ、これで一瞬で終わります。」
こうした構成は、「悩みの共感→解決の提示→商品の紹介」の流れを自然に作っている。
解説:フックとは?
“フック”とは、最初の一言で視聴者を引き込む仕掛けのこと。
映画で言えば“予告編”、本で言えば“帯文”。
動画のフックが弱いと、どんなに映像がきれいでも“興味を持たれる前に”スキップされる。
3. “買ってほしい”が透けて見えると、人は離れる
ショート動画で売ろうとするあまり、ついやってしまうのが「売る気全開構成」。
【NG例】
「今だけ50%OFF!」
「◯月◯日までにご購入を!」
「在庫限りです!」
こうした“押し売り構成”は、視聴者にプレッシャーを与えてしまう。
SNSで求められているのは「情報」ではなく「発見」であり、「共感」であり、「物語」だ。
解説:Z世代の購買心理
Z世代(1996年以降生まれ)は、売り込み臭を極端に嫌う傾向がある。
自分で見つけて、納得して、選びたい。
そのため、「売ってます」より「使ってます」の構成のほうがはるかに効果的。
4. 専門用語と“意識高い言葉”の乱用
クリエイターや開発者がやりがちな失敗が、専門用語の連発。
【NGワード例】
ディスラプティブ
マルチプラットフォーム最適化
インタラクティブUX
こうした言葉に引っかかるのは、一部の業界関係者だけ。
一般ユーザーは「何か凄そうだけど…何それ?」で終わる。
動画の目的が“買ってもらう”であるなら、伝わらなければ意味がない。
5. “カッコよすぎる”は売れない罠
これは意外かもしれないが、映像がカッコよすぎると売れないことがある。
CM的な完成度の高い映像は、もはや“広告”にしか見えない。
一方、ちょっと手作り感のある動画のほうが売れている現象が、SNSでは頻発している。
なぜか?
「等身大感」がある
「使ってる感」が伝わる
「リアルな反応」に見える
つまり、上手さ<リアルさが求められているのだ。
6. ストーリー構成が「完結」してしまっている
ショート動画は1本で完結させる必要がある…と思っていないだろうか?
実は、“未完”の構成が強いフックになることもある。
【OK構成例】
【前編】「これ、普通のコーヒーじゃない」
【後編】「飲んでみたら…予想外すぎた」
連続視聴を促す仕掛け、続きを見たくなる余白、コミュニティで話題にされるようなネタ提供——
これらはすべて“あえて未完”であることから生まれる。
7. “ナレーション依存”構成は、音無しユーザーを切り捨てる
SNS動画は「音ありき」で作られることが多い。
けれど、視聴環境は常に音を出せるわけではない。
「音がないと何が言いたいのか分からない」
そんな動画は、無音視聴者にとっては“ただの映像ノイズ”になる。
対策:キャプションと視覚情報で補完
視覚的に意味が伝わるように工夫することで、音なし環境でも“刺さる動画”にできる。
テキストの出し方ひとつで、CVR(コンバージョン率)は大きく変わる。
8. “誰のため”の動画か分からない
最後に、もっとも根本的なミスがこれ。
「誰の、どんな課題を解決する商品なのか?」
これが動画内で明示されていないと、視聴者は自分ごと化できない。
「よさそうだけど、自分には関係ないな」で終わってしまう。
解説:ペルソナとは?
ペルソナとは、ターゲットとなる顧客像のこと。
年齢、性別、職業、ライフスタイル、抱える悩みまで具体的に設定することで、動画の“言葉選び”や“トーン”が明確になる。
まとめ:売れない原因は、テクニックではなく「構成」
売れるショート動画と、売れないショート動画の違いは「画質」や「ナレーションの上手さ」ではない。
構成こそが命であり、以下のようなミスを回避することが第一歩だ。
■ショート動画でやってはいけない構成まとめ
- 最初に商品をドンと見せる
- 問題提起がない
- 売る気満々なトーク
- 難解な専門用語
- カッコよすぎる映像
- 完結しすぎている
- 音に依存している
- ペルソナが不明
逆に言えば、これらを一つずつクリアにするだけで、
“売れる構成”に近づくことができる。
最後に:あなたの商品を「誰かの物語」に変える力
ショート動画とは、ただの広告ではない。
それは“誰かの物語の一部”になれる可能性を持ったメディアだ。
「伝えたいこと」ではなく、「伝わる構成」を。
「商品」ではなく、「変化」を。
今日から、動画の構成を見直すだけで、あなたの作品は“売れる映像”に生まれ変わるかもしれない。