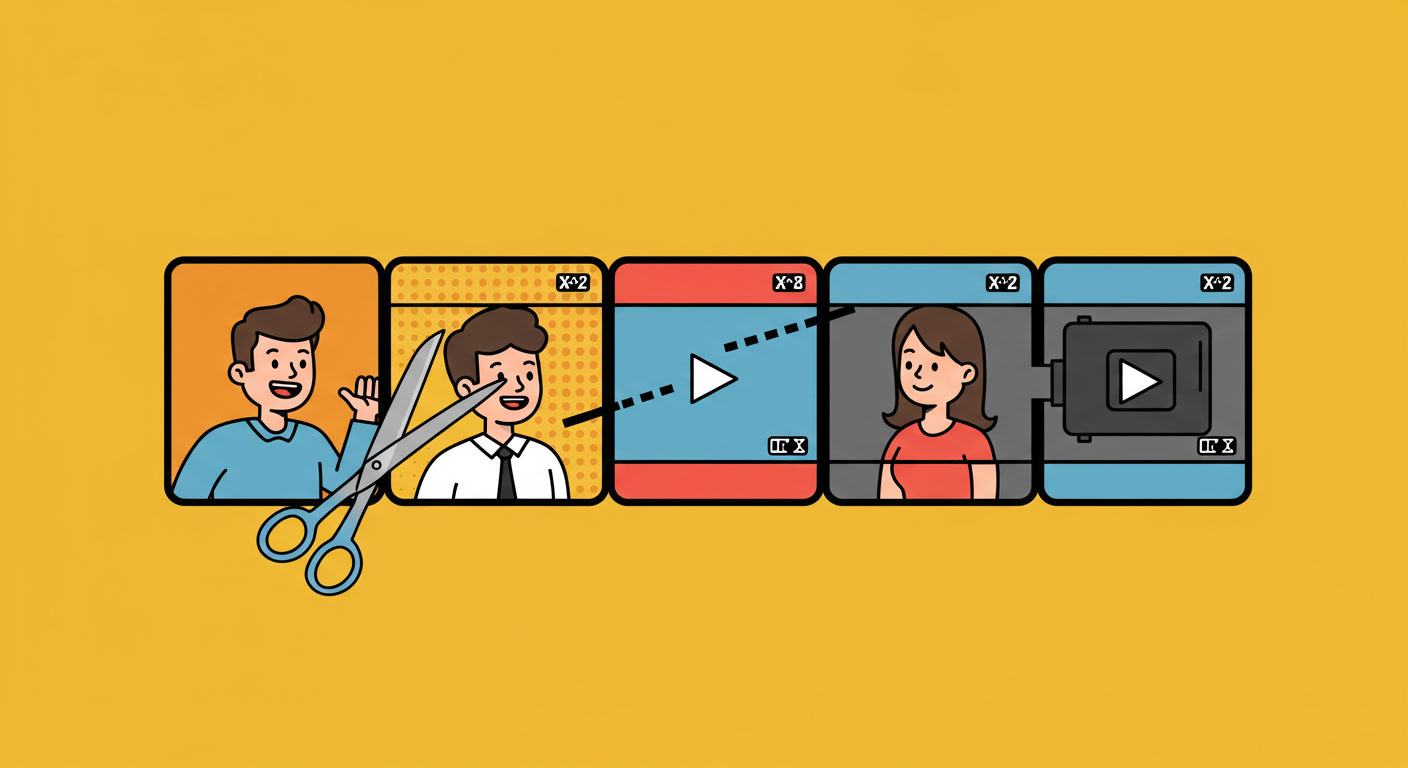インタビュー映像の“間”を削るだけで、見られるPRに変わる 「内容はいいのに、退屈」と言われる映像に足りなかった“編集の呼吸”とは?
はじめに:「ちゃんと話してるのに、なぜ見られないのか?」
映像に映るのは、誠実な経営者、情熱的な職人、使命感を持った医師、プロ意識に満ちたスタッフたち。語られる言葉は本物で、嘘のないメッセージがそこにある。
それなのに、再生数は伸びない。
視聴維持率も10%を超えない。
「伝わらないんだよね…」
そんな言葉が、動画制作者の背中に重くのしかかる。
なぜなのか?
「話が長いから」
「表情が固いから」
「内容がつまらないから」
…本当にそれだけだろうか?
実はそこには、“視聴者の心理的テンポ”と“編集のテンポ”のズレという、見落とされがちな深い問題が潜んでいる。
そしてその問題は、ある“魔法の編集技法”によって、驚くほど簡単に解消されることがある。
それが、「“間”を削る」編集だ。
「間」が、映像のテンポを殺している?
インタビュー映像を観るとき、視聴者はどんな状態にあるか。
それは、待つ準備ができていない状態だ。
YouTubeにしても、TikTokにしても、ショート動画にしても、
今の視聴者は「退屈したら即スワイプ」「違うと思ったらすぐ離脱」することに慣れている。
これは視聴者が“悪い”のではない。情報過多な社会において、私たちは「効率よく情報を取捨選択する能力」を自然と身につけてしまったのだ。
その中で、「えーっと…」「そうですね…」といった“無意識の間”が、映像全体のテンポを壊し、離脱ポイントを生んでしまう。
たとえ内容が素晴らしくても、言葉と言葉のあいだの0.8秒の空白が、
「この動画、なんかダルい」
「今じゃなくていいや」
という感覚を生み出してしまう。
実験:同じインタビュー動画、1つだけ違う編集
ある企業の採用PR動画(社員インタビュー)を例に、次のような編集実験を行った。
Aパターン:撮って出し。間も話し方もそのまま。
Bパターン:言葉と言葉の間の“空白”をすべて削除。話のテンポを1.2倍に。
この2本を同時公開した結果、Bパターンは視聴維持率が約2.3倍に跳ね上がった。しかも、「面白かった」「テンポがいい」「最後まで見られた」というコメントが寄せられた。
何をしたか?
ただ、“間”を削っただけである。
なぜ「間を削る」だけで、こんなにも違うのか?
1. 映像が“考え中の顔”を映してしまう
インタビュー中に多い「考えてる間の沈黙」。
この“間”はリアルでは誠実さを感じさせるが、映像では視聴者の脳に“停止”を感じさせる。
とくにSNSでは、「止まっている=フリーズしている=離脱していい」と無意識に判断されやすい。
つまり、“動いていない=用が済んだ”と解釈されてしまうのだ。
2. 情報密度が薄くなる
間が多いと、1分あたりの情報量が減る。
すると視聴者は「冗長」「時間のムダ」と感じやすくなる。
情報密度を高めると、「得した感覚」が生まれ、視聴満足度と拡散性が上がる。
3. 編集者の「間」の感覚と、視聴者の「間」の感覚は違う
編集者は現場で何度も映像を見ているため、感覚が麻痺しやすい。
ところが、視聴者は初見で“わずか3秒”で判断する。
このズレを解消するのが、「徹底的に間を削る」編集である。
どの“間”を削ればいいのか?感情と文脈を読む
すべての間を削ればいいかというと、そうではない。
「間」は、時に“感情の余韻”であり、“共感のスペース”になる。
例えば、以下のような間は削るべきではない。
- 感情が揺れた直後の「言葉に詰まる間」
- 感謝を語る前の「呼吸の間」
- 失敗談を語る時の「覚悟の間」
これらを削ると、“人間らしさ”が消えてしまう。
削るべきは以下のような「機能していない間」だ:
- 何を言うか迷っているだけの「あー」「えーっと」
- 「次の質問なんだっけ?」という空白
- 編集点のない“映像的に動きのない時間”
感情が乗っていない“間”=削る候補と覚えるとよい。
間を削ることで生まれる「リズム編集」
「間を削る編集」を極めていくと、動画全体が“音楽のようなリズム”を持ちはじめる。
これは、言葉のテンポ・映像のリズム・視聴者の心理テンポがシンクロする状態。
いわば、視聴体験が“快感”になる編集だ。
このリズム編集は、映画やCMの世界では当たり前に使われているが、
インタビュー動画のような“素材重視系映像”では、なぜかあまり導入されていない。
実は、インタビュー映像こそ、“間”のコントロールだけで大化けするジャンルなのである。
インタビュー動画を「PRツール」に進化させるステップ
- 全テイクを文字起こしする
→ テキストで見ると「間」が視覚化され、削るポイントが見つけやすくなる。 - 話の要点を「伝える順番」に並べ直す
→ 質問の順番ではなく、“視聴者の関心が高まる流れ”に変える。 - 機能していない“間”をすべて削る
→ 編集ソフト上で波形や無音区間を活用すると効率的。 - 感情の余韻を残す“間”は残す(むしろ強調)
→ タイムライン上で“残す間”に色付けして見える化すると良い。 - テンポの違いを全体で整える
→ 話すスピードが極端に違う人が複数登場する場合、編集でテンポを均すと統一感が出る。
生成AIとの組み合わせで、さらに進化する
最近では、AIによる「自動文字起こし」「自動無音検出」「自動カット」なども実用レベルになってきた。
Adobe Premiere Proの「Speech to Text」や、DaVinci ResolveのFairlight音声編集、さらには「Descript」などのAIツールは、“間の可視化と削除”を一気に加速させる。
今後は、「撮る→話す→そのままPR映像になる」という未来も、現実になるかもしれない。
特に生成AIと映像編集の融合は、インタビュー動画の価値をこれまで以上に引き上げる。
おわりに:インタビュー映像は、もっと見られる
「インタビュー動画なんて、地味で誰も見ないよ」
そんなことを言われることがある。
けれど、それは違う。
話している内容ではなく、“間”が退屈なのだ。
間を削れば、映像は動き出す。
間を削れば、言葉が届く。
間を削れば、想いが伝わる。
ただそれだけで、映像は劇的に変わる。
動画編集は魔法じゃない。
でも、“編集の呼吸”を知れば、伝わらなかったものが、伝わるものに変わる。
インタビュー映像をPRに変える第一歩は、カメラでも照明でもなく、
タイムライン上の“空白”を見つめ直すことなのかもしれない。